目次
この記事はincu・be vol.53に掲載したものです。バックナンバーはこちらからダウンロード
多様な価値観の中で
再認識する独自性
塚本 真悟 さん
カリフォルニア大学バークレー校
塚本さんは、修士でシンガポール、イギリス、アメリカにそれぞれ短期留学し、その後、アメリカでの博士進学を選んだ。日本を含め4か国を見た塚本さんを、さらにアメリカで研究する道に駆り立てるものとは一体何なのだろうか。
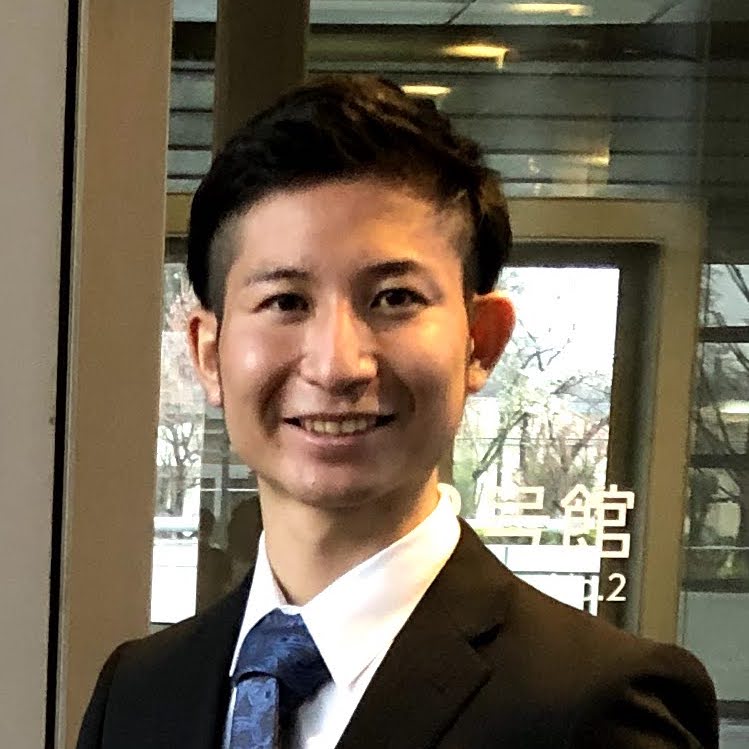
短期留学で海外の博士の実情を知る
塚本さんは、物理的な環境に対する生体応答やその応答機構を解明するメカノバイオロジーの分野の研究に取り組む。いつかは、独自の研究分野を立ち上げ、医療に貢献したい。そう願う塚本さんは、修士課程でまず世界最先端の研究現場を知るために、シンガポール、イギリス、アメリカに短期留学した。そこで、塚本さんが発見したのが、海外で博士進学するという選択肢だった。日本では、将来もアカデミアで自分の研究を突き詰めたい人のみが博士に進み、奨学金を得ることができる人は一握りというイメージがあった。しかし、塚本さんが留学した3か国では、博士学生が国や大学、研究室から奨学金や給料を得るのが一般的であった。かつ博士号取得者の社会的地位が高いせいか、博士学生はアカデミア以外のキャリアも前向きに捉えていた。「好待遇の中で、何より博士が明るく楽しそうに研究していた」日本で気づけなかった海外の博士の実情を知ったことで、塚本さんは海外で博士進学することを決めた。
若い自分を鍛えるならアメリカだ
世界を「知る」ための留学から、世界と「戦う」ための博士進学へ。進学先として複数の国を選択肢に入れた中で、塚本さんが最終的に選んだのは、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校への進学だった。短期留学時に体感した、活き活きと発言が飛び交うアメリカの環境が、自分を大きく成長させると感じたのだ。アメリカでは、修士号の有無に関わらず5年間で博士課程を修了する。他国で一般的な3年と比べて時間はかかるが、その分、若い内に自分をじっくり鍛えられる。奨学金もしくは大学からの TA・RAの給料で生活費を賄うことも可能だ。コロナ禍でも学位取得の形であれば、ビザや別途受給する奨学金の規定の不安こそあれ、状況に応じて授業のオンライン受講や、渡航のタイミングを調整できる。修士での短期留学を経てアメリカのラボとも研究テーマをしっかりと議論する中で、自分の研究との掛け合わせでさらに発展しそうな新規テーマも立ち上がった。将来、独自の分野を立ち上げんとする自分を鍛えられる場所をアメリカに見いだしたのだ。

↑カリフォルニア大学バークレー校に短期留学中、所属ラボのメンバーとの写真
多様な文化から常に自分を客観視したい
研究者は世界戦であり、塚本さんは、メカノバイオロジーを軸にした独自の研究分野の確立を目指す。海外に行くことは、各国の多様な文化の違いを体感し、自分の特徴や置かれている状況を客観視することにつながると、塚本さんは語る。短期留学を通じ現地に行ってこそ、シンガポールの他国より格段に充実した研究設備や、イギリスで活発な欧州間の連携、多様な人材が集まり熱い議論が飛び交うアメリカの文化を知ることができた。同時に、日本での当たり前が当たり前ではない他国の文化を体感したことで、日本人特有の勤勉さが、自分の強みになり得ることを理解できたという。塚本さんは、日本での経験を土台に、次はアメリカで多様な文化に揉まれながら、良いものを取り入れたいと考えている。研究者としての自分を常に客観視してステップを踏むために、海外の場を効果的な環境として捉えているのだ。
(文・神藤 拓実)
|
塚本 真悟(つかもと しんご)プロフィール 東京都立大学大学院システムデザイン研究科機械 システム工学域 2021年3月修了。専門は、メカノバイオロジー。修士1年時に、シンガポール科学技術研究庁A*STAR(3か月、海外インターンシップ SIPGA)、ロンドン大学University College London(2 週間、部局短期派遣制度)、カリフォルニア大学 バークレー校(6か月、トビタテ!留学JAPAN)で それぞれ短期留学。2021年9月よりカリフォルニア大学バークレー校に博士進学。 |
目次に戻る
齋藤 杏実 さん
東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 助教
齋藤さんは、博士後期課程の時にドイツのカールスルーエ工科大学に短期留学した。半年間という比較的短い留学期間において得られた研究の気づきや学びは何だったのだろうか。

日頃の小さな準備がチャンスを呼び寄せる
齋藤さんは、博士時代、自己組織化を利用したペプチドと金属からなる超分子に関する研究に取り組んでいた。もともと海外での研究に興味がありつつも、自身が取り組む研究テーマに熱中していたことから留学に関して具体的なプランを立てたことはなかったそうだ。しかし 2018 年、仙台で開催された国際学会にて転機が訪れた。ドイツから来日していた錯体化学を専門とするルーベン教授とディスカッションする機会を得て、その後指導教官を通じてドイツ留学の誘いがあった。「こうしてドイツ留学はあれよあれよという間に決まったが、日々、研究室の留学生と積極的に話し たり、機会があれば国際的な感覚を身につけたい旨を研究計画などに盛り込んでいたことが指導教官へのアピールとなったと思う。日頃の心がけが間接的に良かったのかもしれない」と齋藤さんは当時を振り返った。
研究の進め方は環境次第で大きく変化
ドイツでは、EUという枠組みにおいて国境を超えた移動や交流に障壁が少ないことから、隣国間での共同研究が盛んである。齋藤さんが滞在した研究室でもスイスの研究者との協力体制があり、積極的に共同研究しようとする雰囲気を感じることができた。齋藤さん自身が留学できたことも、より多くの研究者と研究していこうとするスタンスのおかげだったのかもしれない。しかし、研究は思い通りに進まなかった。驚くべきことに、齋藤さんの滞在した研究機関では試薬の発注から納品までに少なくとも 2 週間はかかったのだ。発注からたった1日で届く日本と同様の納 期を想定していた齋藤さんにとっては大誤算だっ た。とはいえ、ドイツの共同研究に対する積極性といい、試薬の納期事情といい、これらはたった半年間でもドイツに行かないと知ることができなかったことである。今春から助教となり、本格的に海外の研究者とも研究を進めていきたいと考える齋藤さんにとっては、この経験を将来活かせる時がくるはずだ。

↑10か国から集まった多国籍なメンバーと、研究棟のバルコニーでBBQを楽しむ
半年間の留学で得られた気づきは目の前にも
齋藤さんが当時日本国内で所属していた研究室は、超分子化学の分野では国内有数の研究室であり、分析技術に強みがあったことから、共同研究は請負型のものが多かった。一方、留学先で見た、分野が異なる研究者同士が出会い、さらには教授と学生の立場関係なくフラットな関係で議論したり、できるだけ多くと関わろうとする研究の姿勢は衝撃的だった。留学を通して、齋藤さんは様々 な研究分野や実験設備があることを知り、さらには研究価値観の多様性にも触れることができた。 アカデミアとしての道を歩むことになった齋藤さんは、今後自身の研究をより俯瞰して捉えていく必要があることからも、これらの気づきは大きな糧となった。しかし、「コロナ禍の今、海外に行 くのは得策ではないかもしれない」とも齋藤さんは語る。理由は、半年間という短期間での留学が難しくなっており、2〜3年の長期滞在を見据えた動きが必要になるからである。そこで、齋藤さんは国内の他の研究室に目を向けることを提案してくれた。「たとえ同じ国でも研究分野や研究室 ごとに違いはあるはず。国内の研究室の共同研究公募を探したり、隣の研究室の装置を借りに行くといった些細なきっかけでも良いので、他者と大いに交流してその違いを自ら鮮明にしていくことで、研究の幅は広がるでしょう」。(文・内田 早紀)
|
齋藤 杏実(さいとう あみ)プロフィール 早稲田大学先進理工学部応用化学科 卒業後、東京大 学大学院工学系研究科応用化学専攻へ進学。博士後 期課程修了。博士 (工学)。2019年4月-9月の6か 月間、ドイツ学術交流会 (DAAD) 研究奨学金 (短期) を受給し、ドイツ・カールスルーエ工科大学に留学。 2021 年 4 月より現職。 |
目次に戻る
どんな状況でも自分に
できることを積み重ねる
原 啓文 さん
東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 特任准教授
2013年、原さんはそれまで所属していた大学を退職し、 2011年に新設されたマレーシア工科大学マレーシア日本国際工科院(MJIIT)の教員募集に応募した。全く文化の異なる環境で研究機材の設置から研究テーマの立ち上げまでゼロからのスタートに挑んだ原さんが得たものとは。

苦手な海外に行く
「8年も経つとマレーシアでも住めるようになるけど、積極的に選ぶ理由はないし、日本がいい」という原さんは昔も今も変わらず、海外嫌い。ポスドク時代を過ごしたカナダに行く前は英語ができないことが最大の理由だった。英語が話せるようになった今も生活に不自由のない日本で過ごしたいという。それでもマレーシアに行ったのは熱帯という環境に研究対象として魅力を感じたからだ。微生物の探索や機能解析に取り組んできた原さんは、日本では夏しか増えないようなものが 一年中繁殖する東南アジア特有の気候と日本とは 全く異なる土壌環境に興味を持った。当時、温帯地域の微生物研究に関する論文は数多く出ていたが、熱帯地域における論文はほとんどなかった。さらに、執筆者には欧米の微生物研究者が名を連ね、マレーシア研究者が執筆したものは数少ない。このような未知の環境が原さんの研究者魂をくすぐり、直接行ってみたいという想いを掻き立てた。
想定の範囲外で身についたチカラ
MJIIT に着任後の研究室立ち上げは苦難の連続であった。学生を受け入れても機材がないし、機材を買っても場所がない、という状況が2年間ほど続いた。マレーシアではラボ主宰者が奨学金を用意して学生を集める習慣だったことも日本とは異なる難しさだった。このような中で原さんはまず、研究費を獲得して人を集めるところからはじめたが、研究費一つとっても情報が開示されず、日本と同じようにはいかなかった。ようやく見つけた情報も全てマレー語。日本や欧米のやり方がなかなか通じない環境の中で原さんが見出した突破口は「現地の人脈」だった。信頼できる仲間を作り、どこにどんな情報が転がっているのかを教えてもらいながら、8年間かけて何もないところから研究室の立ち上げを完遂させた。「日本にいると物事が進まないことに苛々しがちだが、当たり前が通用しない環境に身を置くことで、それぞ れの環境に応じた最適解を模索する寛容さと建設的な姿勢が身についた」という。

↑MJIIT の教え子たちに囲まれる原さん
自分にできる手段を模索して
マレーシアでの経験の中で「本当にダメだと思った瞬間は山ほどある」と原さんは笑って話す。それでも、ゼロから学生を集め、新しい研究テーマを立ち上げ、実験機材も整備した原さんは、「結局は環境や社会の仕組みのせいにしても何も解決しない。自分ができることをしっかりやっていけば何とかなる」と自身を振り返る。海外で長期の研究経験をしてきた原さんが意識しているのは今までの蓄積に縛られず、新しい研究アプローチを 創りながら次に進むということ。研究の可能性を 広げられるなら、どこにでも行くしどこででもやろうという決意のもと、この春、日本に帰国し、 新たな挑戦を始める。MJIITにはこれまでに日本との共同研究の経験を積んだポスドクもいて、チャットなどを駆使しながら一緒に研究を続けている。これからしばらくは日本を拠点とする原さんだが、また面白い研究の可能性があれば飛んでいくかもしれない。研究者としての寛容さと建設的な姿勢でこれから待ち受けるどんな想定外の状況でも新しい道を切り拓きながら。(文・伊達山 泉)
|
原 啓文(はら ひろふみ)プロフィール 長岡技術科学大学博士課程修了(工学)。カナダ・ブリティッシュコロンビア大学で3年間、東京大学で 2年間のポスドク後、岡山理科大学講師、准教授を経て、 2013年よりマレーシア工科大学マレーシア日本国際工科院 准教授。2021年4月より東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 微生物エコテクノロジー社会連携講座 特任准教授。 |
目次に戻る
海外での研究経験は選択肢の一つでしかない
目指す未来に近づける環境を選び、まさにこれから長期留学に飛び立とうとしている塚本さんは短期間で日本を含む4か国での研究環境を体験し、改めて自分の独自性に気づきました。
研究者としての新しい知識と技術との出会いは国内にもあると考える齋藤さんは 他の研究室を経験することで違いに対してより敏感になり、
未踏の研究に挑戦するためにどこへでも、という原さんはどんな環境でも自分にできることを模索し、研究を進めていく力が身についたといいます。
海外での経験を通して得られるものは 滞在の目的、期間、訪問地域、そして研究者自身によって異なります。一方で、自分の当たり前が通じない環境に飛び込み、自分にしかできないことに挑戦するという点はどの場合にも共通しています。 研究者を成長させる経験の本質は、国境という境界線を越えることではなく、自分の目指す未来にたどり着くための様々な選択肢を模索し、最善の選択をしながら進んでいくことなのでしょう。
さぁ、あなたはこれからどんな選択をしていきますか?
目次に戻る








